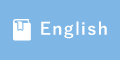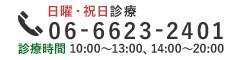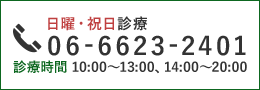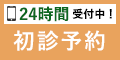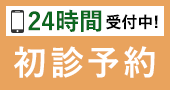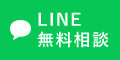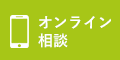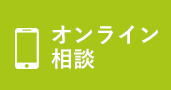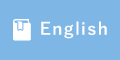当院は、昔から、高校と中学校1校ずつ、学校歯科医として活動させていただいております。
さて、先日、学校歯科医として担当している高校にて、年に一度の歯科検診を行ってきました。小室暁理事長と、3名の先生と一緒に検診してまいりました。非常に歴史のある学校で、今年は他校との統合もあったため、900人近くの生徒さんを勤務医の先生方と一緒に拝見しました。
検診を通じて感じた最近の大きな傾向は、「虫歯の生徒が本当に少なくなった」ということ。これは、日頃からの保護者の皆さまの取り組みや、フッ化物利用、歯科医院での予防処置などが成果を上げているのだと思います。とても喜ばしいことです。
一方で、歯並びに課題を抱える生徒さんは、以前よりもむしろ増えているように感じています。それに伴い、矯正をしている生徒は非常に増えています。特に、「マウスピース矯正(アライナー矯正)」をしている高校生がとても多く、矯正治療がより身近なものになってきていることも実感しました。
”歯並び不正の生徒は多いのだが、治療をしている生徒の割合も増えている”という結論になります。
しかし、今年拝見した中で、未治療の歯並び不正で非常に目立ったのが「開咬(かいこう)」の歯並びです。
「開咬」とは?
開咬とは、奥歯がかみ合っているのに、前歯が閉じず、上下の前歯の間に隙間があいてしまう状態を指します。正面から見ると、笑った時に前歯の上下に空間ができているように見えます。
食べ物を前歯でかみ切ることができなかったり、発音が不明瞭になる、舌の癖(舌突出癖)が見られるなど、日常生活にも支障をきたすことがあります。
なぜ「開咬」になるのか?
原因はさまざまですが、以下のような要因が関係しています
- 小さいころの指しゃぶりや舌を前に出す癖(舌癖)
- 口呼吸の習慣
- 遺伝的な骨格(骨格性開咬)
- 舌や唇の筋力のバランスの問題
- 顎の成長と咬合のアンバランス
中には、顎の骨の形そのものに原因がある場合もあり、矯正治療だけでは改善が難しく、外科手術が必要になるケースもあります。
治療法はあるの?
あります。開咬の治療法にはいくつかの選択肢があります
成長期の矯正治療(小児期・思春期)
成長の力を利用して開咬を改善していく方法。舌の癖を直すMFT(口腔筋機能療法)と組み合わせることが多いです。
成人の矯正治療(マウスピースやワイヤー)
歯の位置を調整することで前歯のかみ合わせを回復します。ただし、重度の場合は限界があります。
外科矯正(手術併用)
骨格性の重度開咬に対しては、外科手術と矯正治療を組み合わせて行う「顎変形症治療」が適応になります。
実はこの治療は、医療保険が適用されることが多いのです。
放っておくとどうなるの?
開咬は、見た目の問題だけではありません。以下のような問題が出ることがあります
- 前歯で食べ物をかみ切れない(機能障害)
- 発音が不明瞭になる(特に「サ行」「タ行」)
- 舌癖や口呼吸により、歯並びがさらに悪化する
- 咀嚼の負担が奥歯に集中し、歯や顎関節に悪影響が出る
特に、顎関節症(あごの痛みや違和感)のリスクが高まるケースもあります。
まとめ:気になる場合は、まずは相談を
開咬の治療は確かに簡単ではありませんが、放置することで将来的に困ることも多い歯並びのひとつです。
また、治療が難しいタイプの歯並び不正だからこそ、保険適用の可能性も大きいと言えます。
ですので一度歯科専門医に相談してみる価値があります。保険適用であれば、経済的な負担を軽減しながら、早期の治療開始が可能となるでしょう。
成長期の今だからこそできる治療もありますし、矯正専門の歯科医院であれば、手術適応かどうかも含めて丁寧に診断してくれます。また、保険での治療が可能な場合もありますので、「開咬かな?」と思ったら、ぜひ一度、歯医者さんに相談してみてください。